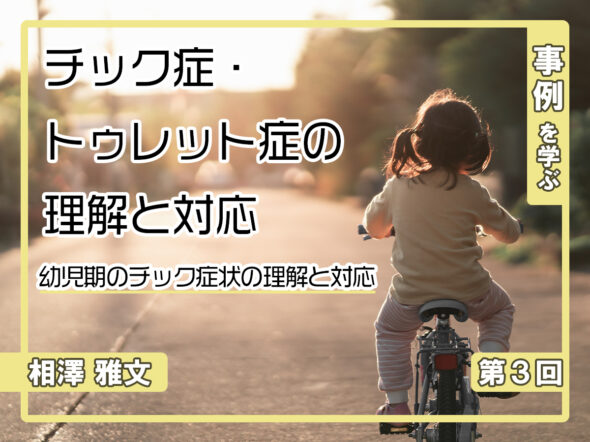チック症・トゥレット症の理解と対応④~学齢期のチック症状への対応~
- #チック症・トゥレット症の理解と対応
- #相澤雅文

目次
学齢期のチック症状についての理解と対応です
1.学齢期におけるチック症・トゥレット症への対応
幼児期には許容されていたことでも就学に伴いさまざまな制約が現れてくることがあります。学校は「小さな社会」と称され、集団生活をしながら人間関係に関するスキルなど、いわゆる社会性発達を育みます。とはいうものの小学校入学後は学習(授業)が中心の生活となります。毎日の学校生活に安心して参加できることや、本人が授業に参加し学習できる環境であることが重要なポイントになります。
一人ひとりのチック症状は異なります。チック症状そのものが授業参加の難しさにつながることがあります。学校での様子をもとに、担任の先生と家庭とで連携する中で、どのような支援が必要かを一緒に考える関係を作ることがまずは大事です。
2.教育環境の調整
先生と話し合うことで、何を伝えれば本人のことを正しく理解してもらえるか、そのポイントが見えてくると思います。その点を具体的に説明して、本人や保護者の思いを伝えていくことを考えましょう。
たとえば,授業中やテスト中などの音声チックの症状は他児の集中を欠く要素となることや、運動チックの症状により、机を力まかせにたたいてしまう、手が動いてしまいノートが取れない、などの症状が現れることがあります。チック症やトゥレット症の子どもはそうした状況の中で、
- 周りの迷惑にならないかを考えてしまう
- 周囲の目が気になり,学校で過剰に気を遣ってしまう
- 気遣いで疲れてしまい学習に集中できない
- 周りの子どもから症状をまねる,揶揄するなどの行為をうける
- 症状がひどくて学校に行けない
などのことがあります。
3.学校での対応
チック症状が重篤化した場合は、授業中やテスト中などで配慮が求められることがあります。授業をオンラインで受講できることや、別室で試験を受けられるようにするなどへの配慮などです。担任を中心とした教職員の理解のみならず、クラスメートの理解を進める工夫も必要です。担任教師の理解が十分であれば本人・保護者の意思確認を行い、担任からクラスメートへの説明をすることで理解が深まることもあります。また、クラスメートへのチック症状に対する自分自身の説明の仕方を具体的に練習しておくなどの対処法を用意しておくことで不安や緊張の軽減につながることがあります。
参考文献
金生由紀子編(2017)『こころの科学194 チックとトゥレット症』日本評論社
NPO法人日本トゥレット協会(2018)『チック・トゥレット症ハンドブック -正しい理解と支援のために-」
酒井隆成(2024)『トゥレット症の僕が「世界一幸せ」と胸を張れる理由』扶桑社
Share