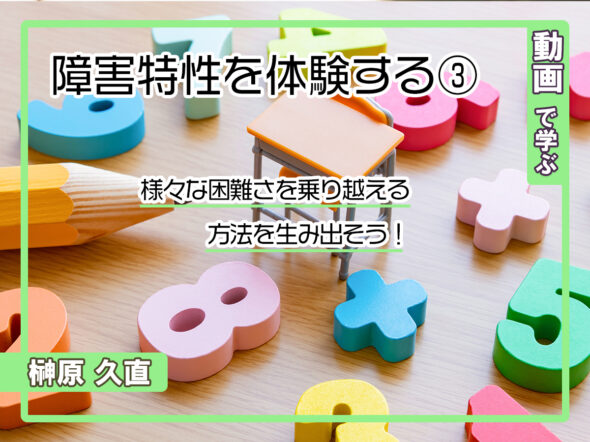校内居場所カフェの実践から考える「きょうだいケアラー」~子どもが子どもをケアする社会構造と学校でできる支援~
- #小西凌
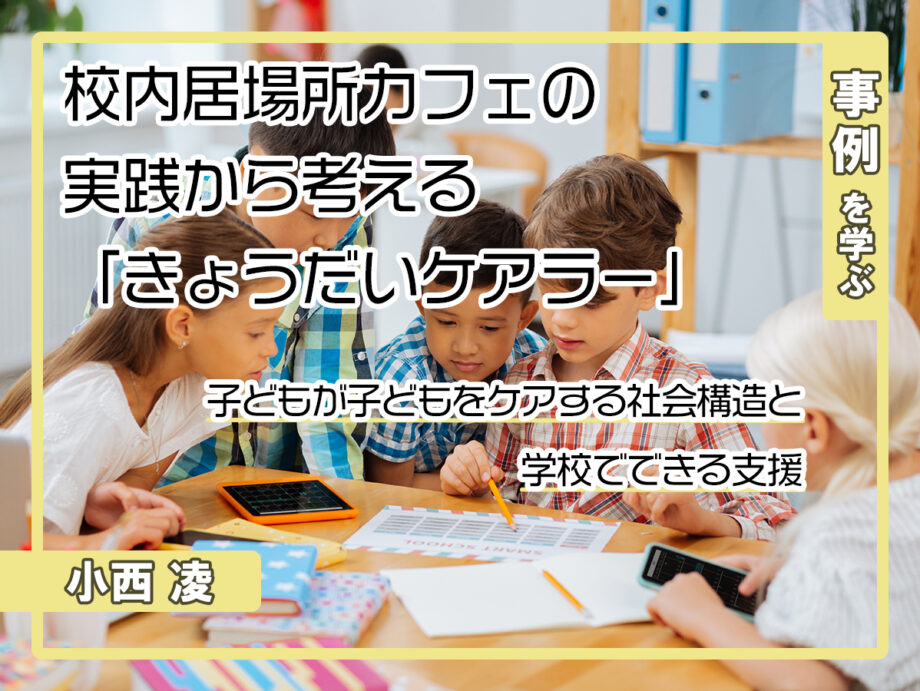
校内居場所カフェの実践を通じ、きょうだいケアラー支援の可能性を考察します。
日本に特徴的な「きょうだいケアラー」
ヤングケアラーとは、大人が担うべき介護や世話、家事などを日常的に行っている18歳未満の子どもを指します。国際的には高齢の家族や病気の親をケアする事例が多いのに対し、日本では「きょうだいの世話」を通じてケアラーとなるケースが目立ちます。(注1)
子どもが背負う役割とその影響
共働きやひとり親家庭の増加、障害や病気を持つきょうだいの存在など、家族構造の中で親の手が回らない部分を子どもが担うことがあります。送迎や遊び相手、食事や着替えの補助、感情的な支えまで、きょうだいケアは「お手伝い」を超えて、子どもの時間や心身に負担をもたらします。本人が「兄弟姉妹だから」と受け止めている場合でも、その背景には「遊びたいけど我慢している」「疲れていても頼られる」という葛藤が隠れています。
こうした負担は、宿題の遅れや居眠り、放課後活動への参加制限といったかたちで学校生活にも表れます。しかし、それを単なる「やる気のなさ」「生活習慣の乱れ」と捉えてしまうと、子どもの実態には気づけません。学校が子どもの変化を受け止める視点を持つことが、支援の入口となります。
「校内居場所カフェ」を活かした、きょうだいケアラーを支える仕掛け
そこで注目されるのが、校内に「子どもが安心して過ごせる居場所」を設ける工夫です。放課後や昼休みに図書室や空き教室を活用し、「校内居場所カフェ」のようなスペースをつくることは、きょうだいケアラーにとって大きな支えになります。お茶や軽食を囲みながら友人と雑談したり静かに読書をしたりする時間は、家庭で背負う役割を一時的に下ろし、「子どもに戻れる瞬間」を与えてくれます。(注2)
筆者もかつて、ある高校内でNPOが主催する校内居場所カフェの運営を手伝った経験があり、そこで「家に帰ると下のきょうだいの世話をしないといけない」と話す生徒に出会いました。その言葉をきっかけに、きょうだいの世話を日常的に担っている子どもがいる現実に改めて気づかされました。校内に安心して過ごせる空間は、そうした子どもにとって単なる休憩所ではなく「自分を取り戻せる居場所」になり得ます。
実際、校内居場所カフェの取り組みは近年全国的に広がりつつあり、地域のNPOやボランティアと連携して運営される事例も増えています。特別な制度や予算を必要とせず、既存のスペースを活かして始められる点でも、現場にとって導入しやすい仕掛けといえるでしょう。
日本でヤングケアラーを語る際、「きょうだいケアラー」の存在に注目することは欠かせません。子どもが子どもをケアするという構造を見直し、学校現場の小さな仕掛けから支援の輪を広げていくことが、子どもたちの学びと成長を守る第一歩となるのではないでしょうか。
(注1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_210412_7.pdf
(注2)校内居場所カフェ全国ネットワーク「校内居場所カフェとは」
https://ibashocafe.net/cafe
Share