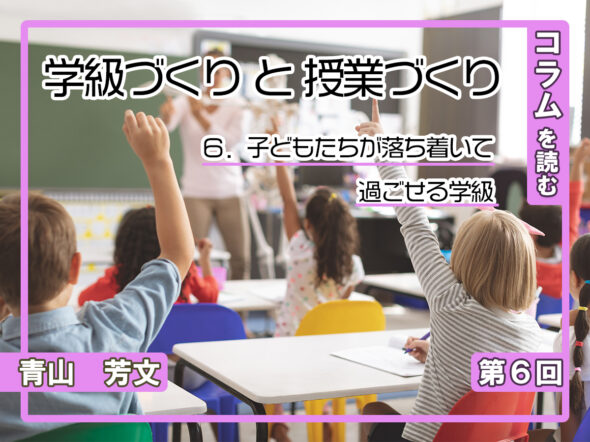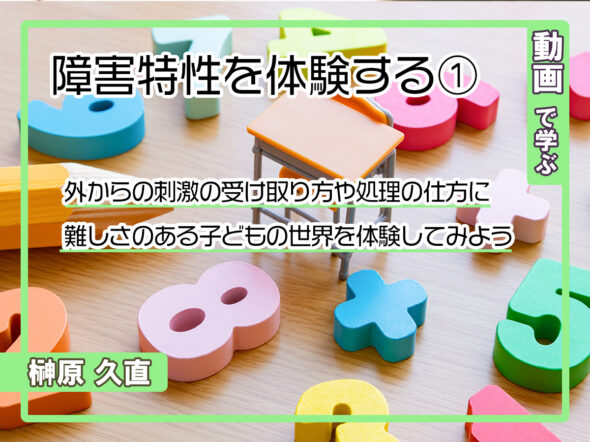学級づくり と 授業づくり⑦~まわりの子どもたちへの理解を促すために~
- #青山芳文

まわりの子どもたちへの理解を促すために大切なのは、まわりのこどもたちへの理解教育ではありません。先生自身がその子への理解を深め、適切な対応を見つけて実践することです。まわりの子どもたちはそれを見て学びます。
「この子のことを学級の他の子どもたちにどのように理解させればいいのか」という声を聞くことがあります。
しかし、その子の特徴をどれだけ整理して正確に子どもたちに伝えても、支援につながる理解には繋がりません。また、理念的に「みんなちがって、みんないい」と指導するだけでは、違いを認め合うことにはなりません。
まわりの子どもたちが「何であの子だけ?」という言葉を発するのは、たいていの場合、その理由が知りたいからではありません。
「私にもしてほしい」とか、それ以上に「先生、それは違うんじゃないの?」という思いの表現なのです。
子どもたちは、担任がその子に、そして自分に対してどんな気持ちを持ってどのように対応しているのかをしっかりと見ています。また、先生が伝えられる程度のことは、日常の付き合いの中で分かっています。
ポイントは一つです。
先生自身がその子への理解を深め、適切な対応を見つけて実践することです。まわりの子どもたちはそれを見て学びます。
自分が親や担任から理解されている、認められていると感じている子どもは、必ず支援につながる理解を深めます。
「学級づくり と 授業づくり」のコラムは、ここで一旦終了とします。
ありがとうございました。
Share