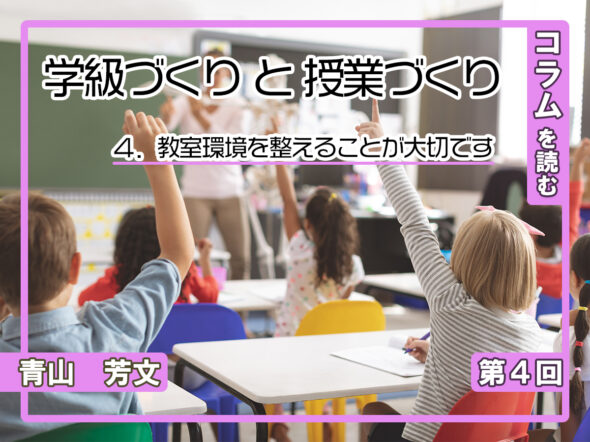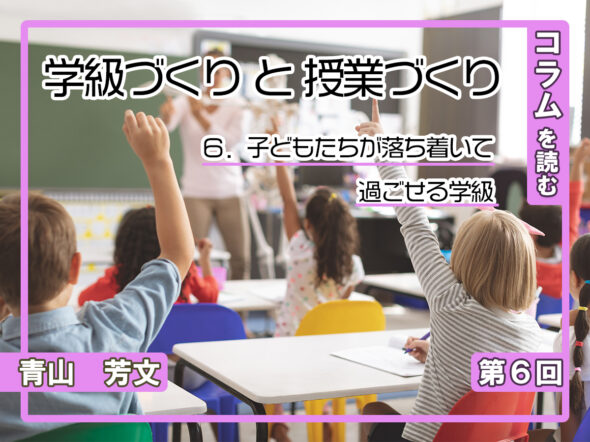学級づくり と 授業づくり⑤~個別支援よりも、まずはユニバーサルデザイン~
- #青山芳文

個別支援よりも、まずはユニバーサルデザインです。
まず大切なのは「ユニバーサルデザインの考え方」です。「特別な支援を必要とする子ども」だけを対象にする「特別な手立て」などではありません。
(ここで言う「ユニバーサルデザイン」とは、最近流行の「ユニバーサルデザイン技法(メソッド)」ではなく、「ユニバーサルデザインの考え方」だということに留意してください。)
いわゆる発達障害のある子どもの中には、担任との「相性」が合えば落ち着いた一年、担任との「相性」が合わなければ立ち歩いたり、教室から出て行ったりして勝手なことをする一年というように、学年ごとに相当異なる様子が見られる子どもがいます。
こうした子どもが(こうした子どもを含めて多くの子どもが)落ち着いて過ごせる学級は、「口やかましくない」「質問や指示が端的で分かりやすい」「話が長くない」「テンポよく授業を進めている」「子どもに多くの活動をさせながら授業を進めている」「教室環境が整えられている」ことなどが共通しています。こうした環境(広義)があれば、いわゆる発達障害のある子どもを含め、多くの子どもたちが安心して過ごし、見通しを持って意欲的に活動することができるのです。
逆に、こうした環境改善が不十分なまま、一部の子どもへの個別で特別な手立てを進めても、ほとんど効果はありません。それどころか、その子も学級全体もますます不安定になっていてしまいます。
まず必要なのは、誰もが「安心して過ごし、見通しを持って活動することができる」環境と手立てなのです。
佐藤愼二先生(植草学園大学特別教授)は、次の言葉で整理されていました。(「通常学級の特別支援/日本文化科学社)
「特別支援の必要な子どもには“ないと困る”支援であり、どの子にも“あると便利な”支援を増やす。」
これだけで「個別で特別な支援」の必要がなくなった子どもも少なくありません。
個別で「特別な」支援をするとしても、そのうえで初めて有効なのです。
Share