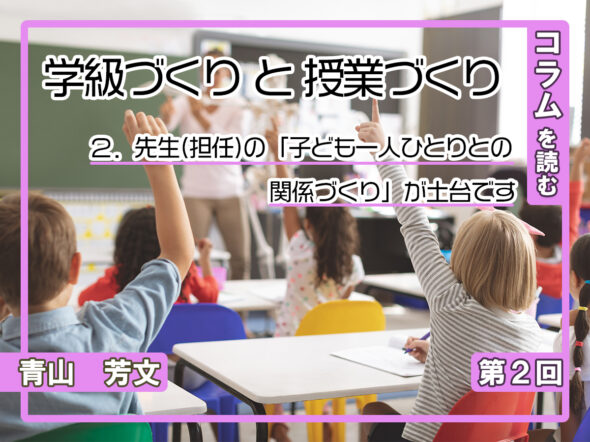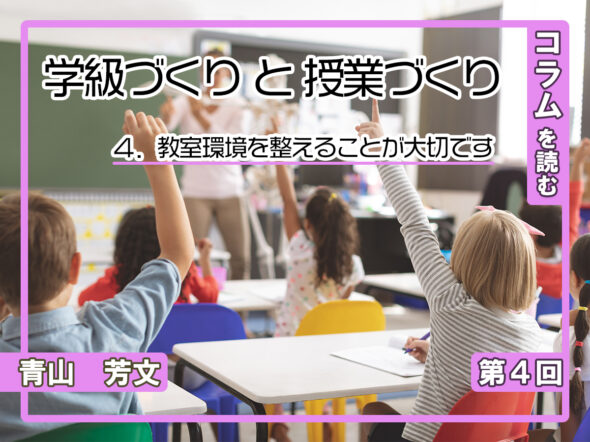学級づくり と 授業づくり③~子ども同士の関係づくりを大切にしましょう~
- #青山芳文
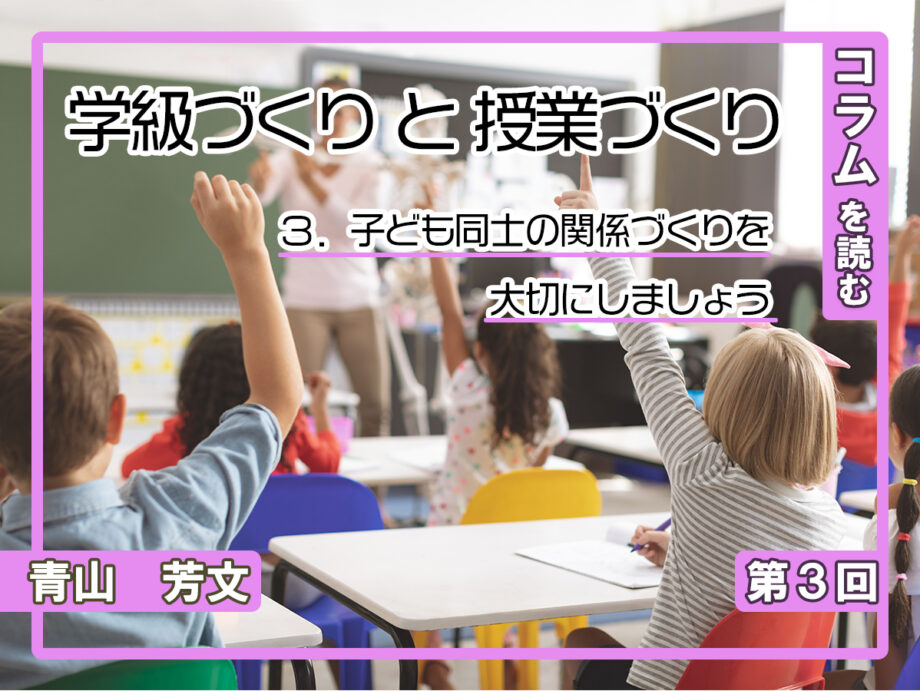
子ども同士の関係づくりを大切にしましょう。
学級は、多くの子どもにとって一日の中で最も長い時間を過ごしている場(集団)です。嫌だからといって別の場に変わることはできません。
学級が子ども一人ひとりの「居場所」になっていることが何よりも大切で、その前提は安心できる子ども同士の関係です。
「誰とでも仲良く」とか「いつもみんなで」と言っているのではありません。好きな人がいれば、嫌いな人もいるでしょう。つらいこと、悔しいことを含め、様々な経験をする中で成長していきます。ただし、「嫌なことはあるけれどもこのクラスがいい」と思えてこそ、嫌な経験も成長の糧になるのです。
子ども同士の関係づくりの支援をすることが大切です。
第一は、学級の子ども同士、「お互いの違いと良さを認め合うのが自然」だと感じることができる学級づくりです。
そのためには、先生(担任)自身が学級全員それぞれのあるがままの姿をまず認め、「ささいな良さ」を見つけて、自然に評価することです。「ささいな良さを見つけて評価する」とは、「ささいなことでも良いことをしたから褒める」という意味ではなく、「その子のあるがままの良さを感じ取って評価する」ことです。他の子どもたちは、それを聞いて、人の良さを認め、自分の良さも感じていきます。
ただし、「自分は大人(親や担任)からそう評価してもらってない」と感じている子どもは他の子の良さを認めることができません。「みんなちがって、みんないい」と教えることを否定するものではありませんが、他の子の良さを認め合う学級づくりのカギは、先生自身が学級の子ども一人ひとりの「ささいな良さ」を認める実践をしていること、そして子ども一人ひとりが先生からそう評価されていると感じていることです。
第二は、仲間の一体感を感じることができる学級づくり、少なくとも仲間の中での心地よさを感じることができる学級づくりです。
そのためには、学級の中に多様で豊かな文化を育てることが必要です。無理をせずに一緒に楽しめる活動があればあるほど、仲間の中での心地よさ、一体感を感じることができます。そのうえで、仲間と一緒にチャレンジする活動、自分なりの役割を果たし人に喜んでもらえる活動があれば、さらに自己肯定感を高め、社会性を育むことができます。
第三は、子ども同士のトラブルは、それぞれの子どもがとりあえず納得することができ、その経験が次に役立つように支援しましょう。
謝らせることが目的ではありません。トラブル解決の支援こそ、人間関係づくりやコミュニケーション能力向上のための貴重な場、ソーシャルスキルを高めるための得難い場です。
気持ちを聞いてあげることだけで支援になる場合、克明に経過を聞いて整理してあげてはじめて支援になる場合、解決の方法を具体的に教えることが支援になる場合など、トラブルの内容や子どもによって様々です。ここで何を学ばせたいか、実際に何を学ぶことができたかを十分に吟味することが大切です。
Share