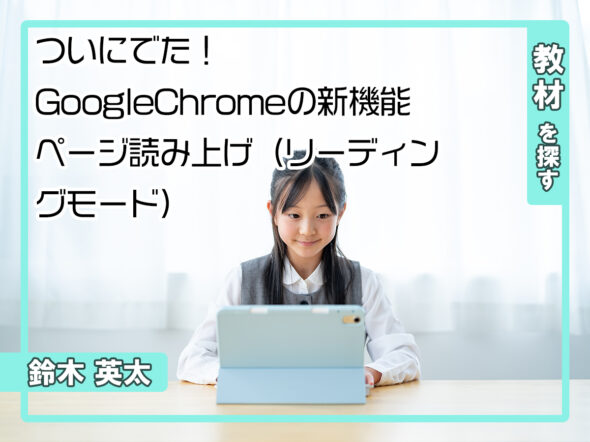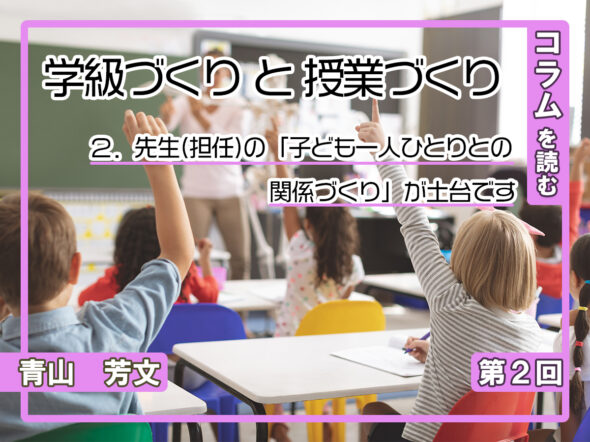学級づくり と 授業づくり①~学校での指導・支援の基本は学級づくりです~
- #青山芳文
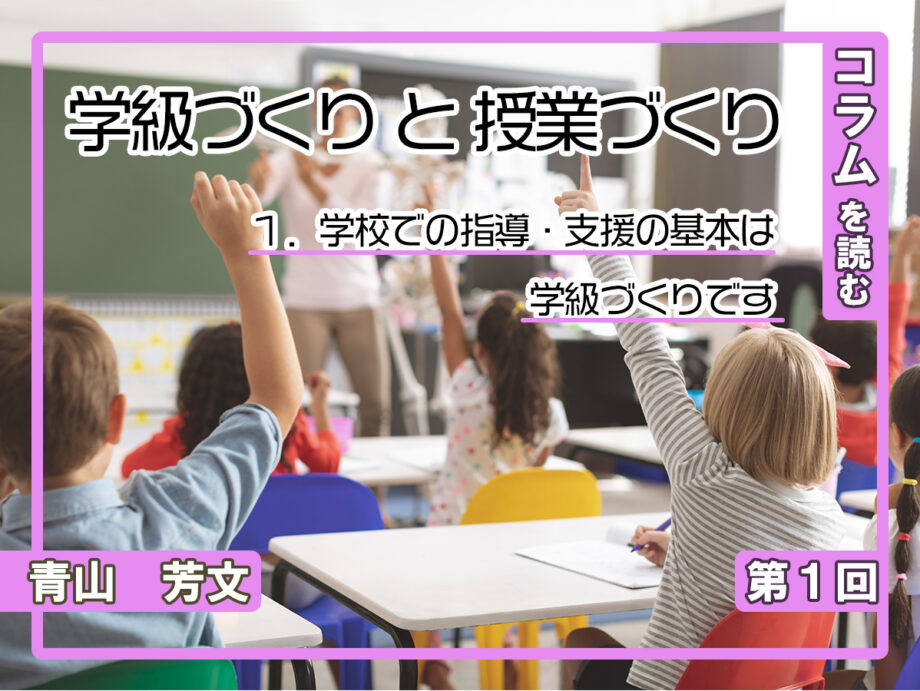
学校での指導・支援の基本は学級づくりです。
<はじめに>
このコラムは、京都教育大学が2009(平成21)年3月に発行した「特別支援教育ハンドブック」(京都教育大学特別支援教育GP実行委員会監修:相澤雅文・佐藤克敏・田中道治・藤岡秀樹編集)の「第7章 学級経営のポイント」(青山執筆)を加筆・修正し、コラム形式に編集したものです。
この資料の発行から15年、学校でも「医療・心理学モデル」による発達障害等の理解、個々の発達障害(発達凸凹)に対する支援の手立て(個別の支援技法)の開発が進み、「子ども一人ひとりの違い」に目を向け、それを尊重しようとする支援が広がってきました。この変化には大きな意義がありますが、それに伴い、「子ども(人)の共通性」に目を向けることが弱まっていないでしょうか。
近代学校教育制度が始まった1872(明治5)年から150年、終戦(第二次世界大戦の終結)からでも80年がたちました。
終戦を機に、富国強兵と忠君愛国を柱とした戦前の学校教育が、子どもを教育の主体者と位置づけ、一人一人の内面を理解し尊重しようとする方向に転換していきました。
一方、学年制で学級を編制し、教科指導を中心に授業をするという基本構造は引き継がれています。「同じ地域に住む同年齢の子ども集団で学級を編制し、子ども集団のダイナミズムを活用して子どもを育てる」というこの基本構造は、同調圧力のリスクなど様々な課題がありますが、私は人格形成や基礎学力の習得などに大きな意義があると考えています。
1 学校での指導・支援の基本は学級づくりです
支援の基本は、「個別理解」と「個別支援」です。
しかし、学校における「個別支援」の基本は「個別指導」ではなく、学級づくりであり、子ども一人ひとりとの関係づくりです。
(「個別の指導計画」のモデルは、アメリカで使用されていたIEP(個別教育計画)です。IEPは“Individualized Education Program”の略称です。「個別教育“の”計画」ではなく、「個別“の”指導計画」(個別化された教育計画)です。
日本に導入するにあたって、「個別指導計画」という名称にすると「個別指導“の”計画」という誤った概念が広がることが懸念されました。そこで、熟語としては不自然にもかかわらず、「個別“の”指導計画」という名称にしたと聞いています。)
Share