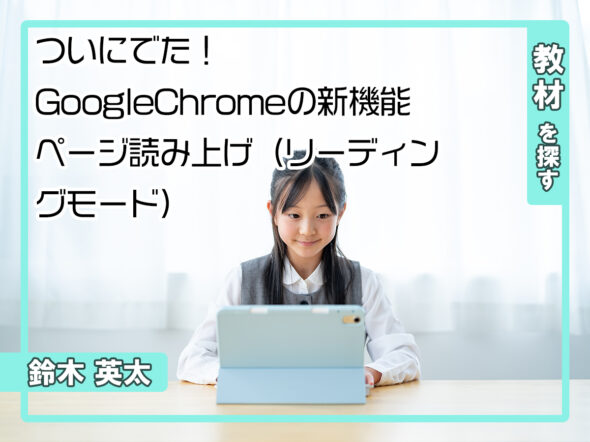保護者の安定化へのアプローチ
- #渡邊陽亮

登校が不安定になっている児童の支援は、その子の置かれている状況が見えにくく、対応が滞ることがあります。
以前、安定して学校に通うことが難しい児童に関わっていました。順調に登校していたかと思うと、突然ぷつんと欠席が続いてしまう…。そんなことがよく起こっていました。児童の状況が見えにくく、生徒指導部会でも「どうすればいいのか分からない」といった声が上がり、支援が止まってしまう印象もありました。
①状況がわからない時は、まずはアセスメントも兼ねて動いてみる
そこで私がまず取り組んだのは、「保護者の思いを聞くこと」でした。そこで、2、3日おきにご家庭を訪ねることにしました。今振り返ると、もしかしたら保護者にとっては迷惑な関わりだったかもしれません。それでも、「動いてみて初めて見えることがあるかもしれない」と考え、アセスメントも兼ねて動き始めました。
②時間が必要だと思って、地道に関わりを作っていく
はじめの頃は、保護者と玄関先での会話もできないことが少なくありませんでした。挨拶だけでもと訪問を続け、「先生も暇やなあ」と言われながら、顔と名前を覚えてもらい、やがてテーブルを挟んで話ができるようになりました。とても地道な関わりで、時間が必要でもありました。
③話を聞き、保護者の状況を受け止める
話を聞く中で、保護者自身の過去について「自分が小学生の頃、丁寧に関わってもらえなかった経験がある」と話されました。さらに、「今でも学校で何かあると、その時の気持ちが甦ってきて、子育てや学校に対して前向きな気持ちを持てず、苦しくなる。」という気持ちを吐露されることも。私はその話を聞きながら、「ああ、そういう思いを抱えてこられたのか」と、ようやく今起こっていることの背景や要因の一部を理解することができました。
④学校として、できること伝える
対話を重ねながら、学校としてできることを伝えていきました。例えば、「困ったことがあれば、本人が先生に訴えて調整することができる」「保護者の悩みについては、加配の教員やスクールカウンセラーに相談することもできる」といった、具体的な支援の仕組の情報を保護者に提供しました。
その前後から、保護者の言葉や態度が少しずつ柔らかくなり、何かあった時には相談してくださるようになりました。校内のスクールカウンセラーによる教育相談でも、子育て相談を行うことになりました。
この保護者にとって必要だったのは、孤立しかけていた保護者の話を聞き、学校の専門家として必要な情報を伝えること。そして何より、学校としてご家庭での子育てに伴走する姿勢をきちんと示すことだったのではないかと感じます。もちろん、思いを聞くことは大切ですが、それだけでは信頼関係を築くには不十分なこともあります。丁寧に耳を傾けた上で、適切な情報を伝えることが、信頼へとつながっていくのだと思います。
⑤保護者の安定化を目指すことも、子どもの大切な環境調整である
保護者の変化とあわせるように、児童の登校も次第に安定していきました。「保護者が安定すると、子どもも安定してくる」という感覚は、これまでのさまざまな場面を振り返っても、思い当たることがいくつもあります。その意味でも、まずはお家の方の思いを丁寧に聞き取り、必要に応じて保護者に伴走するような関わりを続けることは、子どもたちの環境を整えていく上で欠かせないアプローチだと改めて実感しています。
Share