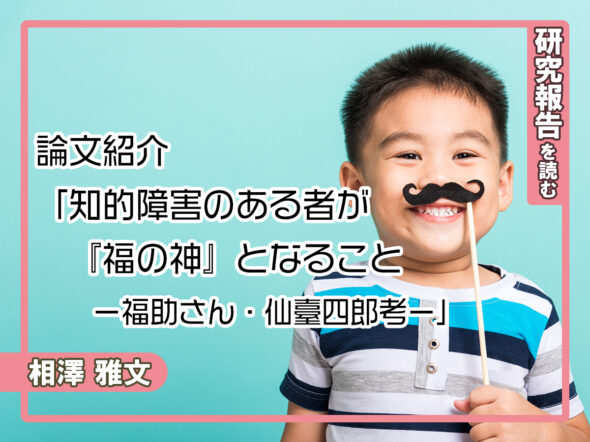小学生ヤングケアラーの声を受け止める学級経営~「家庭の事情」に配慮した関係性の構築~
- #小西凌
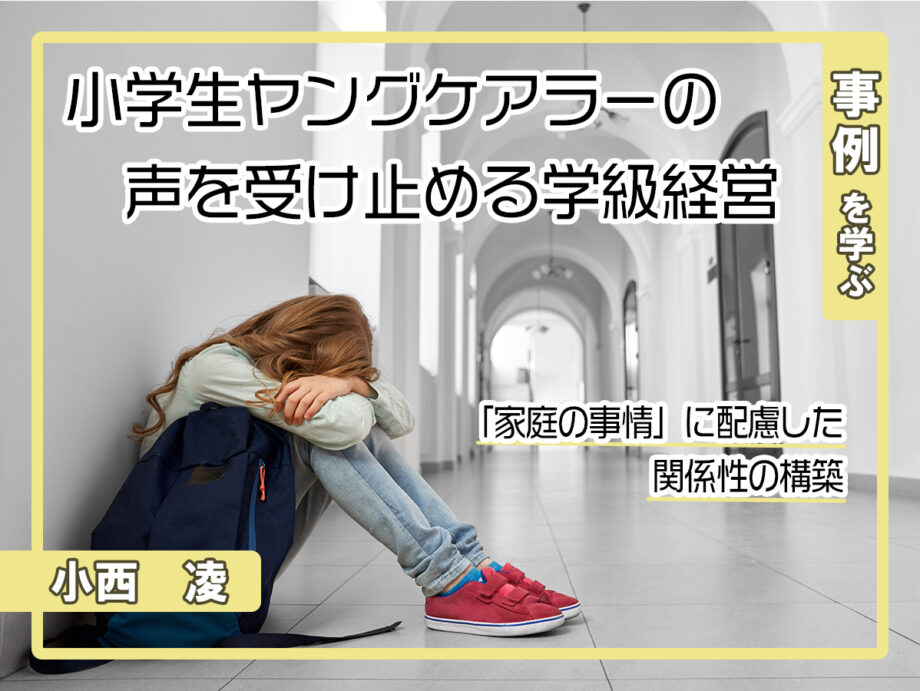
家庭内でケアを担う小学生ヤングケアラーに寄り添う学級経営の工夫と支援の実践を紹介します。
小学生ヤングケアラーという見えにくい存在
ヤングケアラーとは、本来大人が担うべき家族の介護や世話、家事などを日常的に行っている18歳未満の子どもを指します。近年、この言葉が社会に浸透しつつある一方で、特に小学生段階のヤングケアラーの存在は、学校現場でも見えにくく、支援が届きにくい状況にあります。
厚生労働省と文部科学省が2021年に実施した全国調査では、中学生の約5.7%、高校生の約4.1%が「世話をしている家族が『いる』」と回答しています(注1)。小学生に関しては統一的な全国調査は行われていないものの、自治体の実態調査や学校現場の声からは、一定数の小学生が家庭内でケアの役割を担っている実情が見えてきています。とりわけ、障害や病気を抱える親・きょうだいのいる家庭や、ひとり親・外国ルーツの家庭などにおいて、子どもが生活維持の一端を担っているケースが少なくありません。
表面的な行動の背後にある事情を見つめる
筆者が以前、お手伝いをしていた子ども食堂で、ある小学生の男の子について、関係者の方からお話をうかがったことがあります。その児童は、毎朝疲れた表情で登校し、授業中も集中が続かず、しばしば居眠りする姿が見られていたそうです。宿題の未提出や忘れ物も多く、担任の先生は当初、「学習意欲が低いのではないか」「生活習慣に課題があるのでは」と考えていたといいます。
ところが、家庭訪問や面談を重ねるうちに、その子どもが日常的に家事やきょうだいの世話を担っていることが明らかになりました。母親が体調を崩しており、彼は朝、自分の支度を済ませた後、簡単な朝食の準備を手伝いながら年下のきょうだいの面倒も見ていたとのことです。夜は自分の時間がなかなか取れず、寝不足のまま登校する日が続いていたといいます。担任の先生は、「表面的な行動の背後に、こんな事情があるとは想像していなかった」と、当時を振り返っていたそうです。
「困った子」ではなく「困っている子」として
このように、小学生ヤングケアラーの困難は、学校生活の中では「忘れ物が多い」「反応が鈍い」「居眠りする」などのかたちでしか見えてきません。大人が「困った行動」とみなしてしまえば、背景にある家族の事情や子どもが抱える負担には気づけません。重要なのは、「もしかしたら何かあるのかもしれない」と立ち止まる教師の想像力とまなざしです。
安心して話せる関係性を日常の中で育む
まずは日常的な関わりの中で、「話してもいい空気」を育むことが重要です。たとえば、朝の会で「昨日はよく眠れた?」「ちょっと顔色が悪いけど大丈夫?」といったさりげない声かけをすること。連絡帳に「今日も来てくれてありがとう」と一言添えること。これらは特別な対応ではなく、日々の中でできる小さな工夫です。こうした積み重ねが、子どもにとっての安心感につながっていきます。
特に男子児童の場合、女子に比べて自分の悩みや家庭の事情を言葉にして打ち明ける傾向が弱いことが、教育現場でもたびたび指摘されています。「弱音を吐くのは恥ずかしい」「話したところで何も変わらない」と感じ、困難を表に出さずに抱え込んでしまうケースもあります。だからこそ、教師側が日常の中で丁寧に信頼関係を築いていくことが、支援のきっかけとして欠かせません。
一人で抱えず、チームで見守る体制を
また、担任一人で対応しようとするのではなく、教職員間での柔軟な情報共有も不可欠です。「最近ちょっと気になる」「表情が曇っている」といった些細な変化を学年会や校内支援チームで共有し、スクールソーシャルワーカー(SSW)や養護教諭、特別支援教育コーディネーターなどと連携することが望まれます。複数の視点から子どもを見守ることで、教室だけでは見えなかった背景が見えてくることも少なくありません。
受け入れやすい支援から始め、つなげていく
ある学校では、精神的に不安定な母親と、特別支援学級に通う妹と暮らす小学校4年生の女子児童が、家事や育児、妹の送迎を日常的に担っていることが明らかになりました。送迎時に母親の様子を気にかけた担任が管理職に報告し、校内で情報共有されたことで、ヤングケアラーの可能性があるとして支援が始まりました。
家庭が福祉サービスに抵抗感を持っていたため、まずは妹の担任を通じてフードバンクや弁当配達の紹介など、受け入れやすい支援から開始。担任・SSWによる面談と家庭訪問、校内ケース会議を経て、自治体との連絡体制の工夫などが進められました。丁寧な関係づくりと段階的な支援により、家庭が福祉サービスに徐々に接続され、児童の出席状況も改善。中学校進学後も、同じSSWが継続して見守る体制が整っています(注2)。
小さな実践の積み重ねが、子どもを支える
こうした対応は、必ずしも大がかりな制度や予算が必要なものではありません。学校の日常の中で、「できることから始める」姿勢こそが、子どもたちの孤立を防ぎ、支援へとつなげる第一歩になります。
ヤングケアラーであることは、子どもたちにとって「誰にも言えないこと」「言っても理解されないかもしれない」という不安と隣り合わせです。だからこそ、「ここは話してもいい場所だ」と感じられる関係性が、学校という日常の場で育まれていくことが何より大切です。
制度の網目からこぼれ落ちやすい子どもたちに、どう寄り添えるか。その問いに、学級経営という日々の営みの中で、小さくとも確かな実践を重ねていくことが、私たちにできることではないでしょうか。
ヤングケアラーの子どもたちは、「話してもいいのか」「理解されないかもしれない」という不安を抱えています。制度ではすくい取れない子どもたちの声に、教師のまなざしと日々の学級経営で応えていくことが、支援の第一歩です。特別な制度や予算がなくても、学校の日常の中でできることから始める姿勢が、子どもの孤立を防ぎます。
注1)文部科学省「ヤングケアラーに関する調査研究について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/mext_01458.html
注2)ヤングケアラー支援 事例集(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/61786/r5ycjireisyuu.pdf
Share