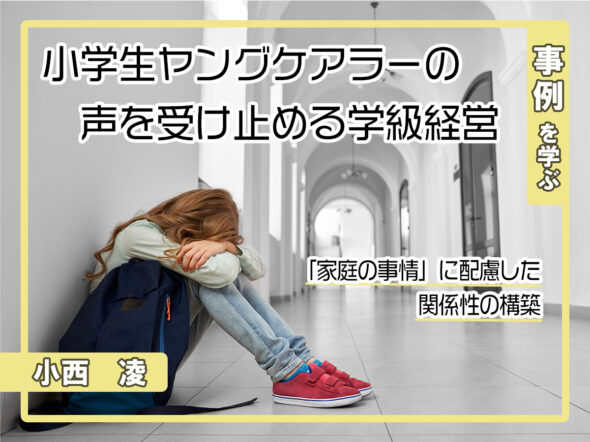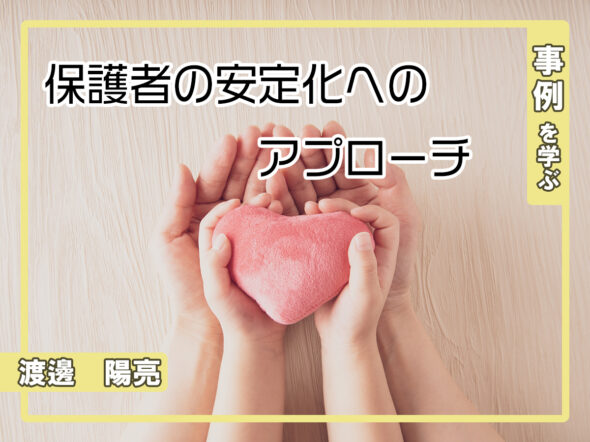机の大きさを調整する
- #渡邊陽亮

近年、さまざまな配慮への認識が高まる中で、子どもたちが学校で使用する教材や道具も大きく変化しています。たとえば、教科書やノートはA4サイズのものが増え、授業ではノートと並行してタブレットやタッチペンを使うことが当たり前の風景になりました。子どもたちが水泳の時間にラッシュガードを着る姿も、今ではよく見られますが、少し前までは珍しいものでした。
このように、教材や学習道具は大型化・多様化しているのが現在の学校の姿です。しかしその一方で、「変わっていないな」と感じるものもあります。その代表例が「机」です。
子どもたちが日々使っている学習机のサイズは、ほとんど変わっていません(少なくとも私が勤めていた20年ほどはあまり変化がありません)。そのため、子どもたちが使用する物が増えた今の教室では、学習時の作業スペースが狭いと感じる場面が増えたように思います。
私が以前勤務していた学校では、すべての机に「児童・生徒用デスク天板拡張器具(通称:天板拡張くん)」を取り付けていました。もともとタブレット導入時の落下防止を目的として導入したものでしたが、使ってみるとそれ以外の効果もありました。
スペースにゆとりが生まれたことで、鉛筆や消しゴムが落ちにくくなり、図工や習字などの活動にも広い作業スペースが確保できるようになりました。その結果、子どもたちが学ぶことに集中しやすくなったように思います。
私の学級では、机の右上を教科書の「定位置」として使っていましたが、天板の端に立ち上がりがあることで、教科書がずれにくくなり、なんだか「いい感じ」です。
かつてのように、1つの教室に35人や40人の子どもたちが在籍しているケースは、今では少なくなってきています。そうした変化を踏まえると、教室の学習環境も、これまで以上に柔軟に見直せる段階に来ているのではないでしょうか。
「学校の机はこういうもの」という固定観念にとらわれていると、変更は難しいかもしれません。でも、このような固定的な学習環境そのものが、子どもたちにとって学ぶ上でのバリアになってしまうかもしれません。「今の子どもたちの学びのスタイルを考えると、机がもう少し大きければ、より学びやすくなるかも」と考えれば、毎日使う机のサイズは、ぜひ見直したい要素の一つです。
「天板拡張くん」のような器具は、既存の机に後付けで取り付けることができるため、財政的・ 体制的な面でも取り組みやすい学習環境の改善になると思います。広い机でゆとりを持って作業をすることは、学習そのものの効果を高めるだけでなく、このような物理的なゆとりが心の安定を助けるようにも思います。
個人的な感想ですが、ものの置き場もないほど散らかった机に座っていると、心まで狭くなるような、なんだかしんどい気持ちになります。反対に、きれいで広々とした机に座ると、「よし、今日もがんばろう」という気持ちになります。机の環境ってとても大切なことだと思います。
<問い合わせ先>
「天板拡張くん」 株式会社ティーファブワークス https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000060875.html
Share