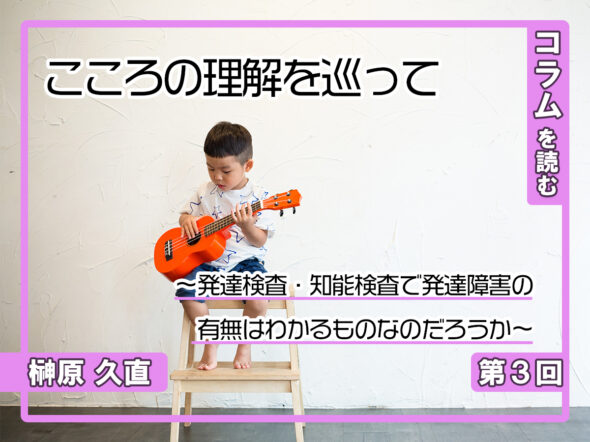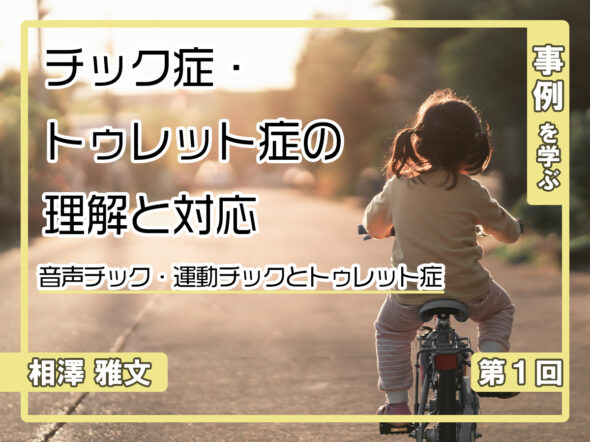こころの理解を巡って~知的・発達的能力以外に大事な視点としての“適応行動”と“社会生活能力”
- #こころの理解を巡って
- #榊原久直
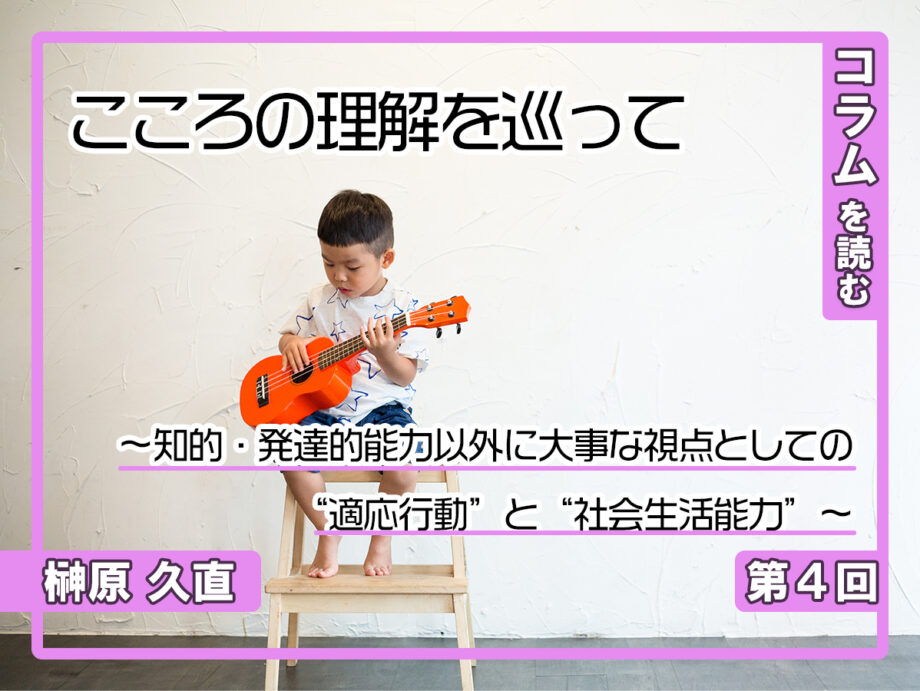
1.“その人らしさ”を映し出す“行動”を捉える
子どものカウンセリングをしていると,子どもたちの様々な表現をその子のこころの現れとして理解するというスタンスを基本的にとるのですが,ここではそうした臨床心理学的な視点ではなく,教育・保育や特別支援,そして子育ての視点から子どもたちの行動を捉える視点を紹介したいと思います。
2. “適応行動/不適応行動”や“社会生活能力”の現れとしての行動
私たちはこころやからだが成長するに伴い,様々な社会生活上の適応的な行動を身に着けたり,社会生活上の能力を獲得していくことになります。そしてこの行動や能力は,先に紹介した発育発達や全般的な知的能力の成長とは,必ずしもイコールではなく,互いに影響し合いつつも,それぞれの能力や行動が別々に成長していくものであると考えられています。
言い換えれば,発育発達や知的能力のアセスメントやその発達の支援と同様に,適応行動や社会生活能力のアセスメントや発達を支援することが重要であると言えます。
知的な発達水準は低いものの社会生活や集団生活ではうまく適応できている子どもの姿や,その反対に,知的な発達水準は高いはずなのに社会生活や集団生活では不適応を起こして苦しんでいる子どもの姿を思い浮かべていただけると,その重要性が想像できるかもしれません。
ここでは実際に適応行動や社会生活能力を測定する心理検査によって測定されることが多い,視点を紹介したいと思います。
…身辺自立(衣服の着脱,食事,排泄などの自立具合)
…移動(運動能力,交通ルールの理解,公共交通機関の利用など)
…作業(手指の操作,道具の扱いなどの作業遂行の力)
…集団参加(友人関係の構築や維持,社会生活への参加の具合)
…自己統制(欲求や衝動を抑え,自分の行動に責任を持つ力)
3. “適応行動/不適応行動”や“社会生活能力”のアセスメントや発達の過程を学ぶ方法
より細かく,具体的な行動として適応行動/不適応行動,社会生活能力を知りたい場合や,そうした行動や能力がどのような順番で獲得されていくのか(発達していくのか)というプロセスを学ばれたい方は,S-M社会生活能力検査,Vineland-Ⅱといった検査のツールや解説書を手に取っていただけると非常に参考になると思います。また,発達検査の代表的なものの1つとして紹介したKIDS(乳幼児発達スケール)という検査も,子どもたちの様々な能力がどういったプロセスで成長していくのかを理解する際に同様に役立つ資料となります。
そして,子どもたちの支援を考える際に,一つひとつの“視点”を思い浮かべることで,様々な角度から子どもの成長を把握するとともに,「今は○○を身に着けた段階だから,それを土台にして,次は○○が身につくように支援したらいいんだ…」という風に支援計画の立案の際のヒントとして活用することをお勧めします。
関連資料
関連記事「こころの理解を巡って」シリーズもご参照ください
Share