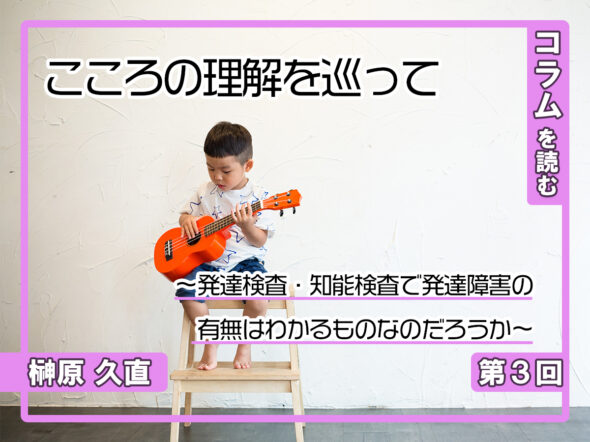こころの理解を巡って~発達検査・知能検査と心理検査~
- #こころの理解を巡って
- #榊原久直

1.“その人らしさ”を理解することの難しさ
子どもに関わる支援に限った話ではないかもしれませんが,「どうしてこの子は…」,「どうしてこの人は…」といった苦悩の声はごくごく当たり前に耳にする言葉のように思います。みんな一人ひとり別の人間であるため,感じ方や考え方が違うのは当たり前のことではあるものの,気づけばどうしても自分自身の中の“当たり前”とのズレを前に,時に傷つき,また時に傷つけてしまうのが,人間関係の難しいところです。では,“その人らしさ”を尊重すべく,それを理解するためにはどういったことを意識することが大切なのでしょうか。
2.“検査”は何を見ているのか
人間の感じ方や考え方の特徴を把握するために,心理学の世界では様々な検査が開発されています。けれども,今日では様々な○○検査ということばがあふれかえり,いったい違いはなんなのだろう…と戸惑われている方も少なくないようです。ここでは教育現場や福祉現場でよく耳にする発達検査・知能検査という言葉と,心理検査という言葉について紹介したいと思います。なお検査の分類には様々な方法があり,ここで紹介する分類がすべてというわけではありませんが,今回は“何を測定するのか”という観点からの3つの分類を紹介したいと思います。
3.知能検査と発達検査とは
発達検査とは“発育発達”と“全般的な知的能力”を測定するための検査です。それに対して,知能検査とは“全般的な知的能力”を測定するための検査です。
発達検査は,乳幼児を含めた発育発達の途上のある子どもに対して,言葉や行動で測定可能な知的発達の水準に加えて,そうした力の土台ともいえるような体の動かし方や姿勢保持,四肢の機能の発達なども含めた,全般的な発達状態(発育発達の状態+知的発達の状態)を測定することができる検査となっております。
他方で,知能検査は,発達検査と比べてやや大きな子どもを対象としていたり,はたまた前者の検査で測定される発育発達の状態を測定はせずに,より純粋に知的発達の状態のみを測定することに焦点化された検査となっています。
代表的な発達検査:新版K式発達検査2020,KIDS(乳幼児発達スケール),津守・稲毛式発達診断,遠城寺式乳幼児分析的発達検査など
代表的な知能検査:ウェクスラー式知能検査(WISC-Ⅴ,WAIS-Ⅳ,WPPSI-Ⅲなど)ビネー式知能検査,K-ABCⅡなど
4. 心理検査とは
これらに対して,性格傾向や精神疾患,障碍特性を測定するための検査がいわゆる心理検査と呼ばれるものです。厳密には,発達検査も知能検査も心理検査の一部として位置づけることが可能ですが,今回は測定できるものの異同を念頭にして,あえて切り分けて説明しています。
性格傾向や精神疾患の症状を測定する代表的な心理検査:ロールシャッハテスト,バウムテスト,MMPI,BDI-Ⅱなど
障碍特性を測定する代表的な心理検査:児童用AQ,PARS-TR,LDI-R,MSPAなど
5.検査や検査結果の有効活用に向けて
様々な現場において検査の必要性や重要性については理解しているものの,実際にはよくわからない…という声はよく聞くものであります。まずは,それぞれの検査が“何を”測定しているものであるのかを理解し,目の前の子どもにどの検査の視点が有効であるのかを考えてみるところから始めてみてください。
関連資料
関連記事「こころの理解を巡って」シリーズもご参照ください
Share