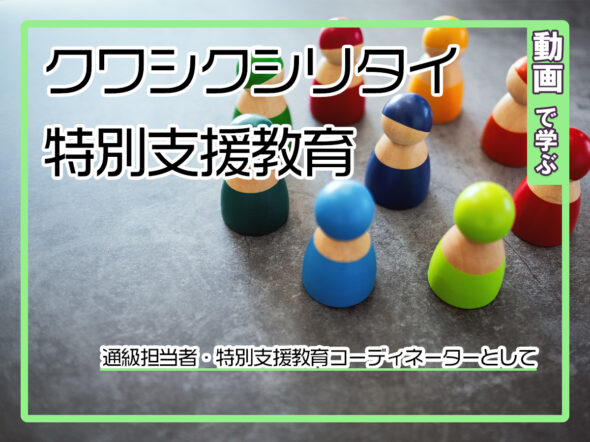こころの理解を巡って~“その人らしさ”を形作る知・情・体~
- #こころの理解を巡って
- #榊原久直

1.“その人らしさ”を理解することの難しさ
子どもに関わる支援に限った話ではないかもしれませんが,「どうしてこの子は…」,「どうしてこの人は…」といった苦悩の声はごくごく当たり前に耳にする言葉のように思います。みんな一人ひとり別の人間であるため,感じ方や考え方が違うのは当たり前のことではあるものの,気づけばどうしても自分自身の中の“当たり前”とのズレを前に,時に傷つき,また時に傷つけてしまうのが,人間関係の難しいところです。では,“その人らしさ”を尊重すべく,それを理解するためにはどういったことを意識することが大切なのでしょうか。
2.それぞれの“当たり前”の土台となる知・情・体
人間の感じ方や考え方には本当に数多くの要因が影響し,かつ時間の経過とともに刻一刻と変化していくものでもあるため,その全てを説明することはできませんが,ここでは便宜的に「知・情・体」というフレーズになぞらえて,3つの視点から“その人らしさ”に影響を与えるものについて考えていきたいと思います。
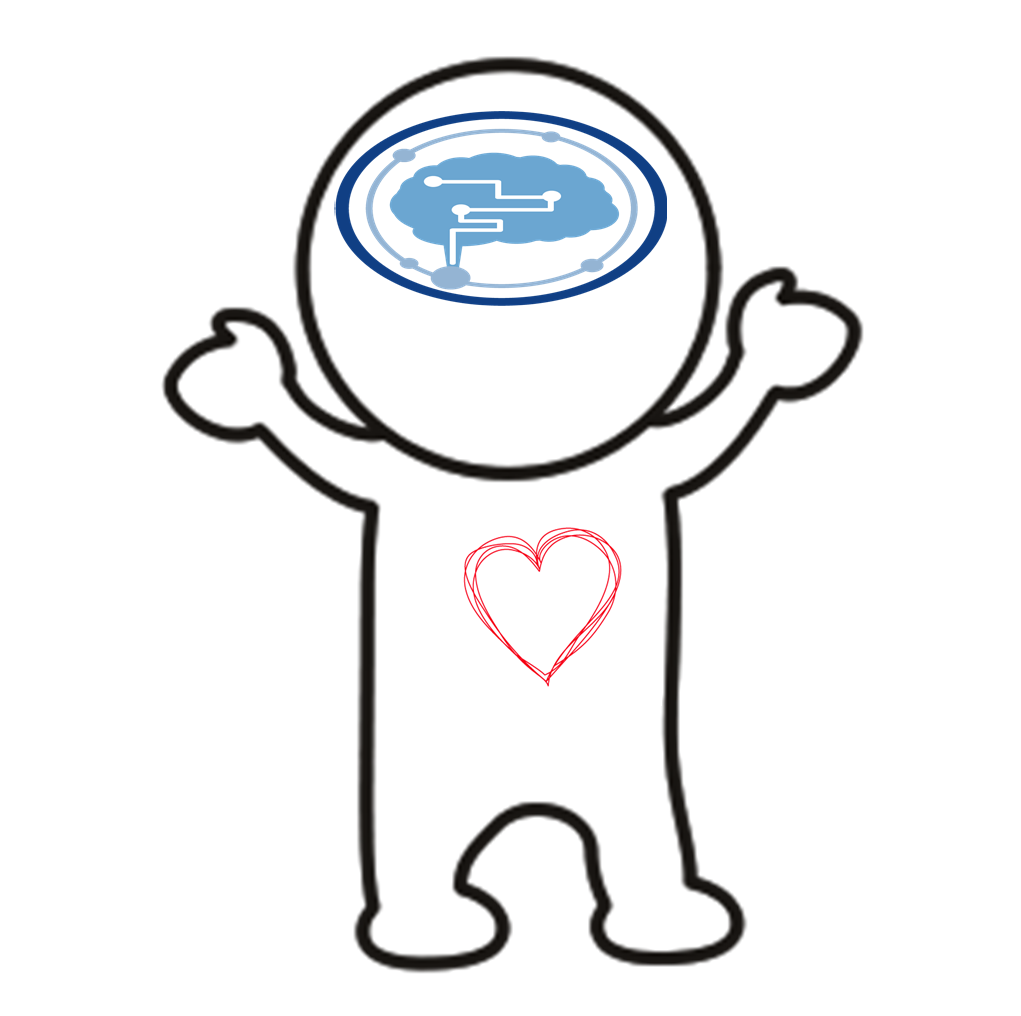
3.その人らしさに影響を与える“知”とは
1つ目の“知”は,その人の持つ脳や神経の特徴です。私たち人間をコンピューターに例えるのであれば,“脳”というセンサーを介して,外界からの刺激をキャッチして,処理し,こころに情報が送られるというような構造をしています。それゆえ,以下のような視点で,それぞれの“当たり前”の土台となる部分についてそれぞれの違いに意識を向けることができるかもしれません。
脳機能や知能:知的な高さ,情報処理の強さ,注意の集中,覚醒の制御…など
脳機能・器質の障碍:統合失調症,自閉症スペクトラム(ASD),注意欠如多動症(ADHD),限局性学習症(SLD),知的発達症(知的障害),高次脳機能障害…など
4. その人らしさに影響を与える“情”とは
2つ目の“情”は,その人の持つ感じ方や考え方の特徴です。私たち人間をコンピューターに例えるのであれば,“脳”というセンサーを介して外界から入ってきた情報や,自分の内側から浮かび上がる様々な情報を処理する際にフィルターのような部分の特徴です。どういった体験を,どういった風に評価し,そこから何かを感じ・考え・判断するのか…など,実は全く同じことを経験したとしても,一人ひとりその“体験”や“意味付け”は全然違ってくるものなのです。それゆえ,以下のような視点で,それぞれの“当たり前”の土台となる部分についてそれぞれの違いに意識を向けることができるかもしれません。
性格:優しさ,思いやり,面倒見,真面目さ,熱血さ,慎重さ…など
愛着関係:安定型/回避型/アンビヴァレント型/無秩序型,反応性愛着障害
精神疾患:抑うつ,強迫性障害,パニック発作,不安障害…など
人格障害:境界性人格障害,自己愛性人格障害,回避性人格障害…など
5. その人らしさに影響を与える“体”とは
3つ目の“体”は,文字通り,その人の持つ体(こころの乗り物・器)の特徴です。私たち人間をコンピューターに例えるのであれば,“脳”というセンサーがキャッチした刺激が,感じ方や考え方というフィルターを経て処理され,生み出された思考や意思を実際の“行動”や“表現”に移す際のモニターであったり,ロボットのボディのようなものになります。全く同じ思考や意思を持っていたとしても,実際に外に表現できる方法は,どういった体で,どういった表現手段を持っているのかによって異なるため,同じ思いをしていたとしても,相手の目に映る表現には違いが生じてくるものです。それゆえ,以下のような視点で,それぞれの“当たり前”の土台となる部分についてそれぞれの違いに意識を向けることができるかもしれません。
身体的な強靭さ;体力,運動神経,健康さ…など
身体的な脆弱さ;肢体不自由,不器用さ,身体の疾患・疾病,免疫の弱さ…など
※近年注目されつつある発達障害の一種である発達性協調運動症の困難さも,厳密には脳や神経上の困難さですが,この“体”という視点で理解する方がわかりやすいかもしれません。
6.当たり前を疑うことの大切さ
このように,私たち人間は誰もが一人ひとりことなる知・情・体の特徴を持つ個別の存在です。けれども,人間は自分と相手は分かり合える・分かち合えるという期待のもとで人間関係を構築していくため,どうしてもこうした人間理解の大前提の部分に差異があるという可能性を忘れがちであったりします。
自分自身と同じような特徴を相手が持っている場合は分かり合いやすいですが,もしコミュニケーションの行き詰まりや齟齬を感じた際には,ぜひこの“当たり前”の部分に差異がないかを考えてみてください。
関連資料
関連記事「こころの理解を巡って」シリーズもご参照ください
Share