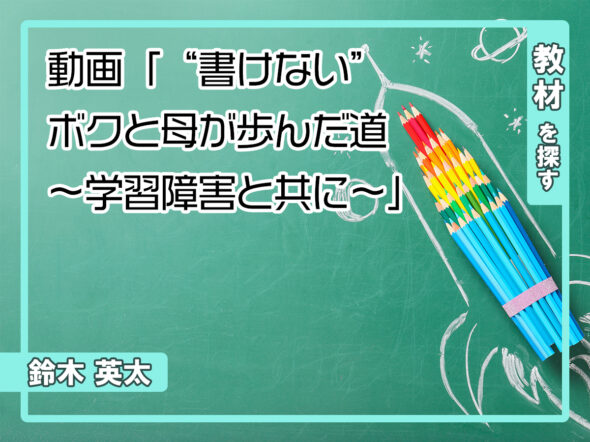不安感と不登校・登校渋り①~母子分離の難しさに関連した不安~
- #不安感と不登校・登校渋り
- #相澤雅文

目次
不登校や登校渋りの背景として、児童生徒が感じている様々な不安感が要因となっているケースがあります。
1.児童の様子
小学校への入学後、毎日登校渋りがあります。何とか取り成しながら主に母親が一緒に登校していますが、校門前で離れられず泣きじゃくり、足にしがみついている事もあります。
どのように理解し、対応していけば良いのでしょう。
2.児童の理解と対応の糸口
こうした状態で考えられることは大きく二つあります。
一つ目は、愛着対象から離れることへの不安感です。
二つ目は、集団生活の中で緊張感、不安感です。
まずは担任の先生とお子さんの行動を観察してみましょう。
母親と別れ教室にたどり着けると、普通に過ごすことができるのであれば、一つ目の離れることへの強い不安と考えられます。私たちは、他者に絶対的に依存しなければ生きていけない「生理的早産」で、産まれてきます。その後、絶対的に依存しなければならない状態から相対的に依存するようになり、少しずつ自立に向けたステップを歩み始めます。その過程は極めて不安定な状態です。幼児期に人形やタオルなどのお気に入り(マスコット)をいつも持っていることがあります。これは安心のためのお守りです。
自立に向けて歩むステップは、何かをきっかけとして崩れてしまったり、退行してしまったりすることがあります。地震や火事などを経験した後であれば、母親と離れている間に「親に何か起きるのではないか」という不安や心配、ということもありますし、幼い妹や弟のお世話に母親の意識が向きがちの場合、自分を見てほしいという気持ちが退行現象(赤ちゃん返り)となって現れることもあります。母親から離れることの不安を無視することや、注意や叱責することはより一層の不安につながります。退行した年齢に合わせて子どもの心理的な欲求を満たすことが大切なポイントとして考えられます。
二つ目の場合は、担任等がスキンシップをすることや、お話しをする機会を多くするなどし、まずは周囲の大人と安心できる関係を築くことが大切と考えます。子どもの学校での状況と対応について、保護者と担任で共通理解を図りながら進めて行くことも大切です。
Share