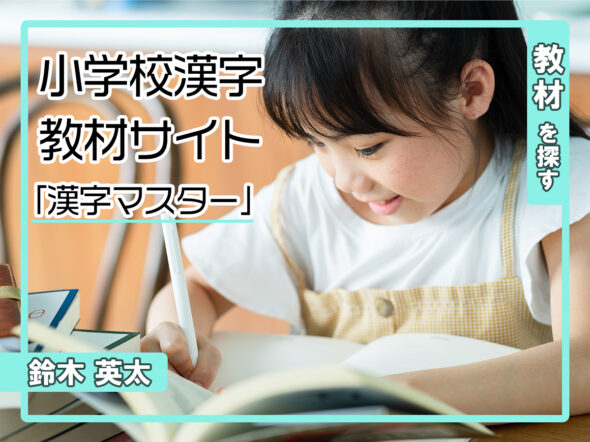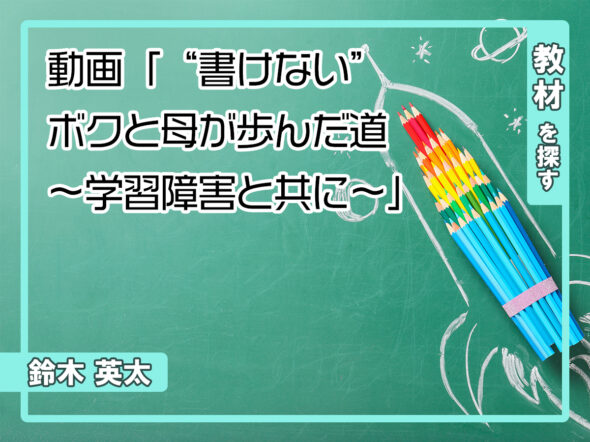現場のホンネ ~個別の指導計画の作成と活用③~
- #現場のホンネ
- #鈴木英太
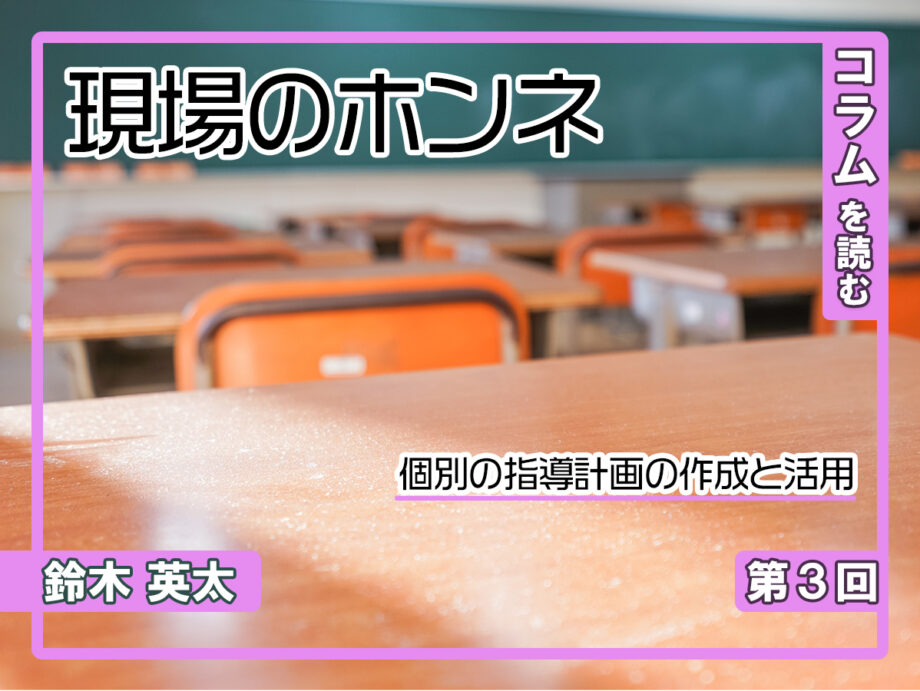
「活用」とは
本シリーズ①と②からわかるように、適切な支援には適切なアセスメント、適切な支援目標と支援内容の決定 が必要で、そのためにはアセスメント票や個別の指導計画を作成が絶対的に必要であることは理解して頂けたと思います。
実はこの構造が「活用」とは何か考えるときに重要なポイントになります。個別の指導計画を作成するプロセス自体が対象の子どものアセスメントを深め、支援に向けて有用なのです。すなわち、適切に作成すること自体が「活用」の一部になっているのです。
「作成」と「活用」は分けられない、という感覚
よく「個別の指導計画の作成と活用」というフレーズを目にしたり、耳にしたりしますよね。なんとなく「作成」と「活用」を独立したものと受け取ってしまいがちです。適切に「作成」したことのある人は「作成」している時点で「活用」を感じているはずです。ただし、これはその経験のある人だけが真に理解できることなのです。
もちろん作成後の「活用」も大切
完成した個別の指導計画は、さらに次のことに活用できます。
・形成的評価による支援の質の向上
・支援目標や内容の共有
・引継ぎ
せっかく作成した個別の指導計画。有効に活用しないともったいないですよね。
すべての先生にわかってもらうには仕掛けが必要
多忙な先生方に「個別の指導計画は作らなければいけません!」と言って作成してもらっても、これまで話をしてきた「良さ」や「必要性」は理解されないことが多いのではないでしょうか。次回は、校内における個別の指導計画の理解促進について考えていきます。 ④に続く
Share