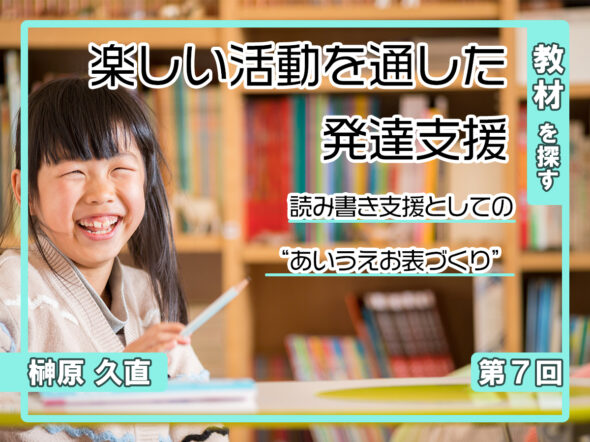楽しい活動を通じた発達支援 ~読み書き支援としての“分身おえかきゲーム”~
- #楽しい活動を通じた発達支援
- #榊原久直
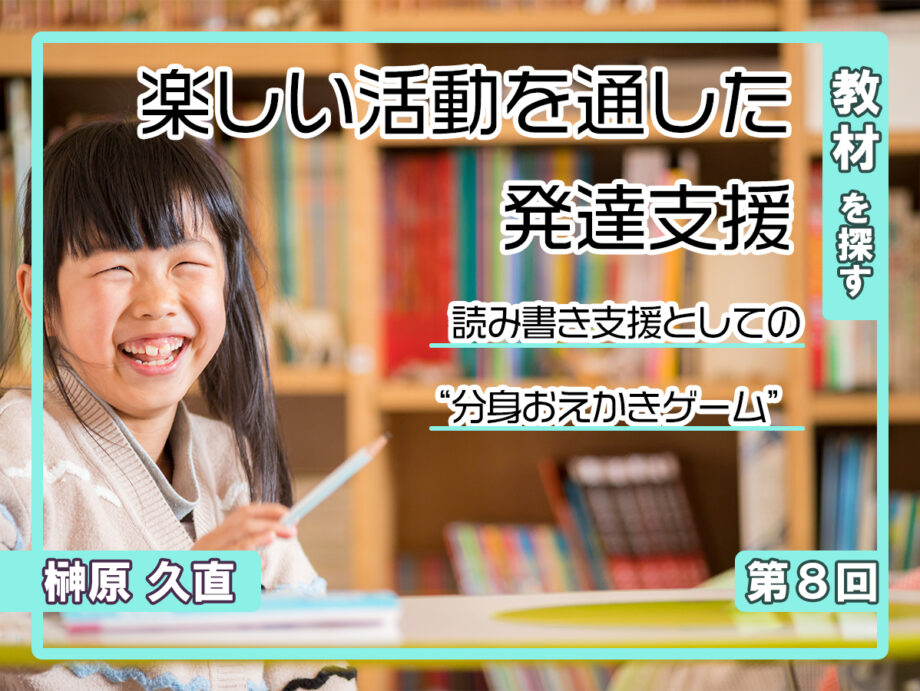
目次
1.楽しい活動を通じた発達支援を目指して
発達支援や療育活動、特別支援などの言葉から、皆さんはどのような活動をイメージされますか。子どもたちの苦手さに対して、なにか“特訓する”・“訓練する”といった修行のような活動を思い浮かべる人は少なくないかもしれません。また、実際にそのような取り組みがあり、それが子どもたちの能力の向上に寄与することもあるのですが、子どもたちの興味関心や意欲をセットで伸ばしてあげたい時には、できるだけ“楽しい”活動を通じて支援ができるに越したことはないのではないでしょうか。
2. 「書き」の困難さを抱える子どもへの支援を考える
「就学を巡る保護者の不安~読み書きがまだできないんです~」の記事にて、子どもがひらがなの読み書きをするという行動を巡って、特に「書く」という行動には以下のような行動や能力、心の動きが含まれているということを紹介しました。
<書く活動>
・文字に限らず線や記号、絵などを描くこと/書くことへの興味関心とある程度の自信
・文字を書くことそのものへの興味関心があること
・(座って書く場合は)座位で姿勢を保持する力
・利き手で筆記用具を保持し、動かす手指の動き
・利き手ではない方の手で、紙やノートを押さえる動き
・文字の形を識別する力
・文字と音をマッチングする力
・50音を理解する力
・頭の中のイメージの通りに筆記用具を動かす力
これらの中で、おそらくひらがなを「書く」という行為の土台となるような部分として、1つ目に挙げた「文字に限らず線や記号、絵などを描くこと/書くことへの興味関心とある程度の自信」を育むことができるような活動の経験を積むことの必要性について考えていきたいと思います。
私たちが子どもの頃、文字を「書く」ということを学ぶ前に、そこに繋がりうるようなどんな遊びをしていたでしょうか。そこには「描く」という遊びがあったのではないでしょうか。ここでは特に、「かく(書く/描く)」ことへの興味関心はあるものの、筆記用具の動かし方(運筆)がまだ自分の思い通りにならずに自信持てていない子どもたちへの支援を紹介します。
3. 読み書き支援としての“分身おえかきゲーム”
「かく(書く/描く)」ことへの興味は芽生えたものの、思い通りに書く/描くことができず、十分に楽しむことができないため書く/描くことに自信持てずにいる子どもたちは少なくなりません。特に、発達の凸凹さを抱える子どもたちの中には、イメージする力と手指を操作する力や考えていることを表現する力のギャップが激しい場合が珍しくなく、「思っているようにできない!」、「書き/描きたいのはこんなのじゃない!」とイライラしたり悲しくなってしまうことがしばしば起こっているようです。
そんな時には、ゲーム的なやりとりの要素があるおえかき遊びが役に立ちます。名称は地域によって異なり、なぜか我が子の通う小学校では「おにぎりゲーム」と呼ばれているそうなのですが、皆さんは同じ絵を何重にもして描くという遊びをやったことはありますか。名前がないと説明がしづらいので、ここでは仮に「分身おえかきゲーム」と称して紹介したいと思います。
ルールや準備物はいたってシンプルです。必要なものは紙と筆記用具、もしくはそれらの代わりになるような物だけです。砂の上に枝で描いても構いませんし、磁気式お絵かきボードと呼ばれるような描画ができる玩具でもよいでしょう。ルールは、ある形の内側に、ひたすら同じ形を何重にも書いていき、一番多く描けた人が勝ちというルールです。
やり方としては、➀参加者はこれから描く絵のお題を1つ決めて発表します。なお、お題は“(外枠の)形”であり、輪郭を描くという点だけ、ルールを共有しておいてください。②参加者全員は、それぞれの筆記用具を用いて、まずは紙面の中にできるだけ大きくその形を描きます。そして③その形と同じ形を少しずつ小さくしながら内側に何重にも描いていき、書けなくなったらストップして、何重に描けたのかを数えます。④一番多く描けた人が勝者となります。


4.遊びをより盛り上げ、経験値を増やすための工夫
この遊びの良い所は、失敗を恐れずに楽しい雰囲気の中で、“形”を意識したり、筆記用具を自分のイメージした通りに動かすという練習ができるところにあります。絵を描くことには興味があるが、上手く書けないで気持ちがしぼんでしまいやすい子どもであったり、文字を書くことに苦手意識を持っていて練習を避けている子どもたちに対して、子どもの興味関心のあるイラストを活用することで楽しく形を意識し、書く/描く練習をする機会を提供する点にあります。
また、お題は無限に選択肢があるため、子どもの興味関心やその移り変わりであたり、描く力に合わせて調整することで、飽きることや自信を失うことを防ぐことが可能になります。
以下に、この遊びのお題の例と、遊ぶ上での工夫を紹介させていただきます。
お題の例:丸、三角形、四角形、星型、おにぎり、ハート、バナナ、ペンギン
(角ばった形だけでなく、曲線を含む形も取り入れてみましょう)
工夫の例:
➀難易度の調整:何重にも書く際に前の絵と線が重なってしまった場合には、その1回分はカウントしないという風にルールを設けると、子どもはより慎重に描こうとするため、運筆の練習になります
(同時に、衝動性のコントロールの練習にもなります)
②制限時間の設定:〇分以内に描ききるという時間制限を設けることで、正確に描くだけでなく、“速く”描くという力を伸ばすことができます
(①と組み合わせると、より高難易度の衝動性のコントロールの課題になります
③複雑な形をお題にすること:“形”を意識する力や、より正確に描く技能を伸ばす機会を 提供することができます
④子どもが好きな形やキャラクターをお題にすること:いわゆる図形をお題にすることがポピュラーではありますが、面白みを増すためには、時々、一風変わったイラストをお題にすることも試みることをお勧めします。

こうした遊びを通じて、書く/描くそのものの技能や自信や意欲を高めることができ、「できる!」、「かける!」、「書く/描くって面白い!」という楽しさを子どもが求めるようになっていくという良い循環が生まれるきっかけを作ることができるかもしれません。
人間だれしも、自分の思い描くものを“表現”ようになることは心の癒しと、何とも言えない達成感や充足感を感じられる瞬間であるため、こうした遊びを通じて楽しく書く/描くことに親しみつつそのスキルを向上する機会を提供することが、子どもの発達を支えることに他ならないのです。
関連資料
関連記事「就学を巡る保護者の不安~読み書きがまだできないんです~」や「楽しい活動を通じた発達支援~読み書き支援としての〇〇~」シリーズもご参照ください
Share